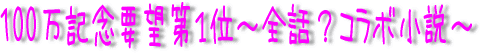
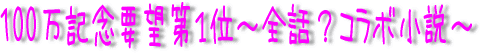
〜某大学学園祭にて〜
「あ、ここだ!紗弓、来栖も早く早く!」
黒髪のショートヘアの彼女は少しつった意志の強そうな目をきょろきょろさせてもう一人の友人を呼んだ。
「もう、芳恵ちゃんたら...」
紗弓と呼ばれた彼女は背中近くまで柔らかく揺れる少し栗色の髪を揺らして引っ張られていく。並んでみればなんと対照的か...浅黒く日に焼けた芳恵に比べると紗弓の肌は白く抜けるようだった。数年前、彼女と同じスポーツをしていた頃はもう少し焼けてはいたが...今も昔も、その洋服の下の肌の白さを知るのはその後ろからけだるそうに歩いてくる青年、来栖遼哉だけだろうけれども...
遼哉はさらさらと流れる長めの前髪を掻き上げながらアンニュイなため息をつきながらもそんな二人の後を後を大人しくついて行く。幾分冷たげな目も、その彼女を見つめるときだけは綻んでいるかのようだった。けれどもいつもの自分の左側の存在をその親友に奪われ不機嫌に一人で歩いてるカレを、女性たちの遠慮がちな視線が絡まってくる。
その独特の雰囲気を醸し出すその彼の顔立ちは、冷たさを表してはいるが綺麗としか言いようがなかった。けれどもここ数年ですっかり大人の色気を加えて凄みを増しているそんな彼を周りが放って置くはずがないが、絶えずその冷たい目線でシャットアウトしてきた。
人目を引くその容姿は遼哉にとっては無用のモノでしかない。いつだってまとわりつこうとする邪魔っけな女性たちを引き寄せてしまうだけのやっかいなもの。自分には紗弓、彼女一人だけでいいと、その視線はたった一人の女性を映し続ける。
そうこうしてる間に距離を開けると早速二人に男どもが声をかけている。催し物の勧誘に格好つけて声かけるのが学祭の習わしだろうか?
同じ高校だった3人は笹野芳恵の彼氏、今村竜次の通う大学の学祭に招かれていた。
「ねえ、ねえ、君らどこの大学?」
紗弓は前から可愛いらしかったのが、化粧を初めて大人っぽさを加えてずいぶんと落ち着いた可愛らしさに変化していた。穏やかに微笑むその仕草は世の男性を癒すだろう優しさをたたえていたし、少し下がった眉は気弱そうにも見えかねないがぱちりと開いた瞳を細めて笑うと、遼哉が気を張っているときでも自然と和むのだ。とどめはピンクのグロスを乗っけた唇。わずかに開いて男をその気にさせる。それが遼哉には気が気ではない。
「なぁにしてるのかな?」
遼哉は不意に紗弓を後ろから羽交い締めにして照れる紗弓ににっこりと笑いかけた。
「やだ、遼哉ったら...もう!」
いきなりの所作に紗弓が照れて焦る。それ以上のことなんかしょっちゅうしてるのにいつまでも慣れない恥じらいをもっている紗弓。その後ゆっくりと顔を男性どもに向けると、笑ってない目で威嚇しながら微笑みを返す。
「いや、別に...俺たちは、なぁ?」
最近凄みを増してきた遼哉のその笑わない笑顔で迫られて、学生たちは目を合わせるとさっさと散らばっていく。その視線は紗弓だけでなく芳恵にも名残惜しそうに視線を残していた。
(なんだ、こいつら笹野も目当てだったのか...)
日に焼けて、相変わらず大学でソフトボールなんてやってるけど、芳恵は以前に比べると女らしい体型になって、そのボーイッシュな顔立ちも少し化粧するとなかなかそそる仕上がりになっていると遼哉は思っていた。
(竜次が心配するはずだな...)
笹野の彼氏である今村竜次も最近化粧をはじめた彼女を心配している。もっともその彼氏のための化粧なのだからしかたないのだが、その変化は自分が与えたものだと、まじめな今村は気がついていない。そう思って遼哉はくすくすと笑った。
「何がおかしい?来栖、今日は紗弓とお泊まりだからって今からおかしくなってんじゃないでしょうね?このエロ青年!」
「笹野...おまえその口何とかならないのか?ったく...竜次の前だとずいぶん可愛くなるらしいのにな?」
にやりと笑ってそう言い返えされて、芳恵は耳までぼっと赤くなった。
「ば、ばか、何の話ししてるのよ!もう、もう、これだから男同士って...」
ぶつくさ言う笹野を相手にしてる間に紗弓がいなくなったことに気がついた。
「あれ、紗弓がいない...」
視線を巡らせると二人組の男に囲まれてにこやかに笑っているのを見つけた。遠目で見ても背の低い方の男は綺麗な顔で、女なら安心してついて行ってしまいそうなタイプだ。
「おい、紗弓!」
駆け寄ると相変わらずにっこりと笑って遼哉を迎える。
「へえ、キミがこの娘のカレシ?うん、すっげえ、いいな!その印象度、溜まらないね...冷めた風に見えるのに、この子を見る目が熱いね。なぁ、よかったらこの娘と一緒に君も撮らせてくれないか?」
背の高い方の男にいきなり遼哉の肩ががしっと掴まれて、耳元でそう言われた。男でも羨ましくなるような低めの甘い声に遼哉は一瞬くらっとした。
「な、なんだよいきなり...」
目の前の男は意志の強さを全面に押し出すきつい眼孔で遼哉をしている。印象度では自分よりよほどあるのではないかと遼哉は思ってしまう。
あまりにいきなりな申し出に遼哉は焦った。紗弓の方を見るけど少し困った風に微笑んでるだけだ。仕方なくもう一人の男の方を見て驚いた。短い髪、細身の身体、背の割に小さめの頭に涼しげなその顔...よっぽどこっちの方がきれいな女顔だよなと思った瞬間、あることに気がつく。モデルのように無駄のないスタイルにユニセックスなファッションだが紛れもない、その男は女性だった。
「あのね、映画に出ませんかって、この人たちが...映画研究会の監督さんなんだって。」
「はぁ???」
その二人は久我広海、紺野竜姫と名乗った。
「う〜ん、こっちに住んでるんじゃないのか...惜しいな、すごくいい素材だと思ったのに。」
「ほんと、広海のモロタイプだったのに、惜しいね。二人とも...」
友人のところに遊びに来ただけだと告げると久我と名乗った男はがっくりと肩を落とした。
「あんたら恋人同士だろ?すごくいい感じだからさ、その感じフィルムに残しておきたかったんだ。あんたのその冷めた目が彼女見るときにさっと変わる...そこが撮りたいんだよ。頼む、今だけでも少し撮らせてくれないか?絶対に悪用他用はしないから。」
そう言って名詞を差し出してくる。
「しかしな...」
「なんだったらオレの撮ったフィルムを見てくれないか?それからでもいいから...」
「何でそこまで?」
「う〜ん、言葉で説明するのは難しいんだが、オレがあんたのカノジョを映したのを見れば納得してくれると思うけれどもな。自分のカノジョがどれだけ魅力的か、あんた自分がどれほど女性を引きつけているかなんて客観的に見てみたくはないか?」
にやにやと笑いながらそう言う久我は、遼哉たちが同じ歳だと判ると急にあんた呼ばわりだった。なんだか見透かされてるモノがあるような気がして遼哉は悔しくなる。
「な、そっちの人、あんたの彼女?」
少し耳を寄せて聞くと、久我はああと頷いた。
「オレなんか撮らずにあっち撮れば?彼女なんかすごく客観的に見てもすごく魅力的だけど?」
遼哉がにやっと笑ってそう言い返すと久我は一瞬怒ったように顔をしかめて、その後小さく『もう撮った』と口にした。その表情がなにかもろ崩れたといった感じで、遼哉は自分と同じく一人の女に溺れてる男の臭いをかぎ取ってに再びやりと笑う。それが久我には気に入らなかったのか、その目が一瞬細まって遼哉を見据えた。
「遼哉?あれ、久我...どうした?」
二人、軽くにらみ合い状態に入りつつあるのを女性二人が心配げに見守る中、ずんずんと割り込んできたのは今村だった。
すっかり日に焼けて、鍛え抜かれた彼の身体はしなやかな筋肉を身につけて、高校時代に比べると何倍もたくましくなっていた。顔つきも以前の少年ぽさもすっかり抜けて、精悍な男性の顔つきになっている。和兄のような無骨な男っぽさに憧れる遼哉としては、そんな今村が羨ましくも思える。柔道をやっても、体格はそう変わりはなく、少々筋肉質になった程度だった。そんな今村の後ろに控えた笹野がやけに華奢に見た。
「ああ、今村、おまえの知り合いだったのか...じゃあ、撮影に通ってもらうのは無理なのか。」
二人は同じゼミをとってるらしい。意外な組み合わせだが、温厚でくそまじめな今村は、女性を引きつける男とのつきあい方には遼哉ですっかり慣れたと思っている。
「今村、おまえもいい根性した友人を持ってるな...」
未だにらみ合いを続けながら久我がそう言った。
で、結局久我たちが撮ったという映画を遼哉たちは見た。
どこかノスタルジックな想いを起こさせる映像、学生特有の気負いやなれ合いの入っていない、意外と本格的な短編だったのに驚いていた。実は遼哉は結構映画好きだった。まあ、TVやビデオで気に入ったのを見る程度だが、紗弓と出かけて話題の映画や、秀作を探して小さな映画館に足を運ぶこともある。いつもえっちなことばかりしているのではないのだ。
「台詞、ほとんどなかったね...」
「でも、なんだか魅せられちゃったって感じ。」
紗弓と芳恵が上映されていた視聴覚室から出てくるとそうぼそっとつぶやいて深いため息をついた。
「切なくなっちゃった...」
紗弓なんかは少し目が潤んでいた。遼哉は思わず引き寄せたくなるのをぐっと押さえながら紗弓の横に立った。
「案外、あの男...」
本物かも...そう思われてならなかった。
「久しぶりだな、ここは...」
「ふうん、ここが浩輔が通ってた大学かぁ...なんだかいい感じだね。」
「ほんとによかったのか?ついてきて...うちのクラブも優勝したからといって先輩にこんなモノ送ってくるなんて、ったく魂胆見えてるって言うんだ。」
三谷浩輔が手に持ってひらひらさせてるのは母校の大学のラグビー部からの学祭の招待状だった。優勝記念に学祭で対OBをやるので来てくれとのことだった。もちろん、浩輔には後輩と先輩からの執拗な参加要請の電話が脅迫電話のように鳴り続けたことは過言ではない。異常に人気のあった浩輔がでるとでないとでは観客数が違うことを踏まえた後輩どもの策略なのだが、3代前のキャプテンであった浩輔が参加しないわけにいかなかった。ほかにも社会人チームに入った者など多数参加している。彼らも観客稼ぎの要員だ。
そしてせっかくの休日に、仕方なく新妻を引き連れて大学までやって来たってわけだ。妻の奈津美の手には土産の菓子折が下げられている。浩輔の肩の上にはビールケース、浩輔のラフなジーンズ姿にあわせて、奈津美はデニムのマーメードラインのスカートを履いていた。姉弟に見えないこともないが、はたから見てもわかるその甘い雰囲気は隠せなかった。
「先輩!やっぱ来てくれたんっすね!!あれ...そちらは?」
現キャプテンのこの男は1年の時浩輔がかわいがっていた園村という男だった。弟のいない浩輔にとって明るくてやんちゃなこの男が可愛くてしょうがなかったのだ。こいつとサッカー部の磯部と二人連んでは浩輔の元に遊びに来たり、飲みに連れて行けとたかられたりしたものだ。特に園村は、何に置いても秀でている浩輔に憧れ、下手したらそちらの世界と言っていいほどべったりしていたのだ。
「あぁ、半年前に結婚したんだ。妻の奈津美、こっちは後輩の園村。おい園村、貴重な休日を割いてきたんだからありがたく思ってくれよ。」
あこがれの先輩が紹介したのが、学生時代付き合ってた綺麗なだけの女どもと違い、どう見ても年上だけど、女性としても、なによりキャリアを感じさせるその佇まいにレベルの高さを感じて驚いていた。今日は長い髪を緩やかに落としてカジュアルな服装の中にも落ち着いた女らしさが漂う。にっこりと笑うと優しくて暖かい笑顔に、男だらけの部室内はしばらくぼうっとしたむさ苦しい男性どもでいっぱいになった。そして大人の女の魅力を身につけた奈津美を従えた浩輔に羨望の眼差しが集まる。
「三谷先輩!すげえです!もう結婚されたなんて...それもこんなきれいな人となんて、羨ましすぎですよ!で、どうやって口説いたんですか?」
その台詞は何代かのキャプテンがそろうたびに浩輔に浴びさせられることとなる。
炎天下の中試合は始まった。社会人でやってる者もいるし、歴代の実力者を集めたOBチームは若さ以外では現役チームにもひけをとらない。もちろん浩輔もトップクラスの選手だったのでプレーには困らなかったが、いかんせん運動不足がたたってしまった。前半終了のところで足がつってしまったのだ。
「大丈夫?浩輔...」
心配げにのぞき込む奈津美をにクイクイと指で呼ぶと、汗にまみれた笑顔でその耳元に甘く囁いた。
『大丈夫、今晩の体力は残してあるから...』
その男臭い臭いと笑顔にくらっとなって赤面する奈津美だった。
「あれ、さっきまですごく走ってた人いなくなっちゃったね。OBチームの人。」
「ほんとだね、きれいに走る人だったなぁ。」
紗弓の問いに芳恵がうっとりと答えるものだから今村の眉がぴくりと動いた。
4人は映画を見た後、少しだけ撮影させてくれという久我の申し出を渋々承諾し、今村の所属する野球部で遊んでるところをと撮影された。その後は別れてフラフラと見回っているところ、やたらと人がグランドに隣接しているサッカーラグビー場に集まっていくのでそのまま流れてきたのだ。元々スポーツ好きの4人は思わずラグビーの試合に見入ってしまった。
「野球部は試合しないの?」
「ああ、もうすぐリーグ戦あるからね、今日はバッテイングセンターとストラックアウトだけだよ。さっきやっただろ?二人とも見事に景品勝ち取ったくせに...」
紗弓と芳恵がそれぞれの部門で女性部門の最高得点あげて周りを驚かせたのは言うまでもない。いつの間にか今村が用意したソフトボールで紗弓がパーフェクトを、芳恵がバッティングで的を当ててホームラン賞をとった時点で周囲から感嘆の声が上がった。二人とも今日に限って見た目とのギャップが大きすぎたのだ。二人ともスカート姿でやるものだから遼哉も今村も気が気でなかった。もちろん遼哉もかなりの成績だったのだが男にはかなりきつめに設定してあって何ももらえなかった。
「けど遼哉が投げてるとこ初めて見たけどさ...おまえ、高校でも続けてたら...」
今村がそう言いかけるが遼哉は笑って首を振った。
「オレは何事も中途半端だったからな...おまえみたいにのめり込めなかった、それだけだよ。まあ、その分アレにのめり込んでるけどな。」
そういって紗弓を指さす。
「だな...オレは今は芳恵を一番に出来てないけど、彼女ががんばってるからこそ、やって行けるんだ、大好きな野球を...」
芳恵も今村も教師を目指している。いずれどこかの中学や高校で教えたいと思っているのだ。自分たちが大好きな野球とソフトを...遼哉はふと自分のやりたいことを考えたが、すぐに頭を振った。
一足先に部室に戻って着替えようと思った浩輔は奈津美に肩を借りて、部室に向かった。
そのとき、どこかの部室の裏で抱き合う二つの影をみて思わず苦笑した。若いな、と...当時付き合っていた女とそこら辺でキスした覚えがあるのは奈津美には言えない。しかし近づきかけて二人は驚いたどう見ても男同士のキスシーンだった。
「よせ...やめろってば...んっ」
男の手が相手の腰を引き寄せて自分自身を押しつけているセクシャルなキスだった。女のように細い声をあげる男は少年のようでやけに色っぽかった。見過ごそうと思ってもその前を通り過ぎなければラグビー部の部室まで行けない。
「やっ、広海...んっ」
そのキスは首筋に降りていく。スピードを上げたくとも痛む足ではそうもいかなくて、奈津美をちらっと見ると彼女も真っ赤になっている。
「あれは女の子よ...ほら」
奈津美が小さく言うのでちらりともう一度見るとシャツのボタンがはずされた隙間から肩に紐がある下着が見えた。紛れもなく女性...男の手が次第に大胆になりシャツの下で蠢いている。
「んっ、やぁ...」
「竜姫...っ」
彼女の名前を呼ぶその低く甘い声を耳にしながら、二人はそっと立ち去った。
「浩輔も学生時代...した?」
「え?」
「こことか...外とか...」
部室に戻っていきなり奈津美にそう聞かれて浩輔は返答に困った。ここではないが、誰もいない資料室や小教室でことに及んだことは何度かある。まあ、彼も若かったのだ。しかしそう聞いてきた愛しい人の顔をみて浩輔はその身体をすっと引き寄せた。もっとも足が痛いので座っているベンチの上にだが...
「ね、ここで、する?」
「な、何言ってるの?あたしそんなつもりで聞いたんじゃないわ...」
昨夜は帰るのが間に合わず今朝早く帰ってきた浩輔は未だに奈津美とは繋がっていない。そういう意味では、若い浩輔にとって、1週間がとてつもなく長いのだ。
「おいで、そんなこと口にして僕をその気にさせたんだからたら、ちゃんと責任とらなきゃ。」
自分の興奮したモノを奈津美に押しつける。
「学生時代の僕の相手に嫉妬するなら僕だって昔のあなたの初恋の相手にだって嫉妬するけど?」
膝の上にのせた彼女に舌を絡め、唇から首筋へ...先ほど垣間見た学生同士の情事のようにシャツの下から手を忍び込ませてゆっくり胸をもみし抱き、胸の蕾をきゅとつまんでみせる。
「あっ...んっ、ねえ浩輔...恥ずかしい...」
「もし...奈津美と同じ大学で会っていても、こうやって手に入れたと思うよ。学生時代の僕だったらソレこそところ構わずやっちゃったかもだね?」
「もうっ...」
「ああ、だからここで...ずっとこの1週間我慢してきたんだ。奈津美が欲しくて、欲しくて...」
浩輔は奈津美のスカートをたくし上げ、下着の上からゆっくりと彼女の感じるところを刺激し始めた。
「ああぁっん、やぁん...だ、だめっ...んっ」
奈津美は溜まらずに声をあげる。そのまま浩輔は下着の横から中指を滑り込ませて、濡れはじめたそこをゆっくりと押し開きかき混ぜはじめる。
「こんなに濡れてるのに、だめ?」
「うっ...くうっ...」
差し込まれた指が折り曲がり奈津美の切ない部分を撫で続ける。それをしばらく続けられると彼女もたまらない。
「もう...許して...浩輔」
切なげに目の前で喘ぐ愛しい妻の中に入り込みたくて待ちかまえている自分自身を解き放ち、奈津美を誘導すると下着の隙間からあてがい自ら沈めさせる。浩輔自身を飲み込んだそこはもう溢れんばかりの泉であった。
とろんとした瞳、半開きになった唇...普段の奈津美からは想像も出来ない、扇情的な表情の変化を繰り広げる。
「このままするよ...奈津美」
そのまま、ずんと奥まで突き上げると奈津美の身体が大きくのけぞった。
「ああぁっ!!」
その瞬間締め付けられて、溜まらなかった。1週間も放って置いた身体はすぐに爆発しそうになる。
「うっ...ごめん、奈津美、帰ったら...ゆっくり、して、あげるからっ!」
その締め付けから逃れるかのように激しく何度も突き上げる。
「あぁんっ、浩輔!」
奈津美自身も自ら動いて浩輔を求めた。恥ずかしさで真っ赤に染めた目元が揺れる。震える唇が彼女の限界を伝える。
「やっ、もう、だめ...っ!!!」
「あぁ...くっ、もう...あぁぁっ!」
ひくつく奈津美の中で浩輔が最大の快感を伝えて震えて果てた。
「はぁ...節操なしの夫でごめん、奈津美。」
いたずらっぽく笑う浩輔に彼女も照れたような微笑みで答えた。
「けどいつもと違うのも、またいいんじゃない?」
「もうっ馬鹿!」
耳元で囁やかれて奈津美が恥ずかしそうに浩輔の肩に顔を埋める。その瞬間知らず知らずに彼のモノを締め付けて、再び元気を取り戻しそうになる。
「いくらなんでもこんなとこで2回戦は出来ないよ?」
苦笑いしながらそっと自分を引き出すと『また足つりそう』と呻いた。
「広海、なんでっ、こんなとこで...もうっ!」
胸まで開かれたところで竜姫は力を振り絞って広海を引きはがした。
珍しく撮りたい人たちを見つけて広海は上機嫌だった。その後はもう用事はないとここまで引っ張ってこられたのだが...だからといって部室の裏手に連れ込まれるとは思わなかった。誰も来ないと思っていたのだろうか?しっかりと一組のカップルに目撃されたと言うのに...
「ん?おまえが悪いの。いったいオレは何週間、ほっとかれたと思う?」
「し、仕方ないじゃない、学祭の準備大変だったんだから...」
「だったら学祭の準備委員になんかなるなよ!」
広海先ほど欲望を果たせなかった憤りでイラついていた。
「そのおかげで体育館での上演も、競争率の高い視聴覚室もとれたんでしょうが!それで2週間ぽっちほっておかれたからといって、ここはないでしょ!」
「じゃあ、部室ならいいのか?」
「馬鹿っ!しょっちゅう誰かが出入りしてる!」
「なら...ここでさせろよ?」
「そ、そんなことしたら今晩泊まってあげない!学祭を口実に美咲のとこに泊まるって言ったけど、やめる!今夜はそんなに用事ないからゆっくり出来るって思ってたのに...」
「ほ、ほんとか...」
「ん...ほんと。覚悟も、してる...」
「...辛い状態なんだけどな...そっか...じゃあ、ま、我慢すっか。」
そう言って久我は竜姫を抱きしめ、空を見上げた。
「おお、広野、おまえまだいてくれたのか?」
「先輩?いえ、あの、ここで待ってたら友人たちが来るんですよ。」
広野将志は今年入った大学の学祭でクラブの主催する模擬店で先ほどまで焼きそばを焼いていた。料理は得意な将志は重宝がられ、いや、かなりこき使われぼろぼろだった。昼過ぎに彼女である槇乃が友人の姉でもある勢津子と顔を出したのに、忙しさのあまりに話も出来なかったのだ。それでようやくこの時間に休みをもらい、槇乃さんへメールでここで待つと送っておいたのだ。
「ああ、あの年上っぽい女性と一緒だったおまえの友達か?」
「はい、友人とその姉貴と、もう一人がオレの彼女です。」
「え?まさか、あの、背の低い方の女?うそ...おまえ、一年の分際であんないい女とぉ!!」
先輩の攻撃を受けながらも、あのへそを曲げた年上の彼女を思うとため息がでる。話しかけようと呼んでも来ない、知らん振りして、ほかの男ども(先輩だけれども)だけに愛想振って、オレにはにこりともしない。ここにも来てくれるかどうか...
もっとも...昨夜、いや、明け方まで自分が攻め立てて足腰立たなくした上に、朝出かけにもう一回乗っかったもんだから、起き上がることすら出来なくなって、朝からここに来ると公言していたのに来れなかったからすっかりご立腹なのだ。ごめんと謝っても、『知らない、馬鹿っ!』といってそっぽ向かれてしまったのだ。その割には焼きそば4人前持って行ったけれども...おまけに博士と小池が一緒にくっついて回ってるだろうと思ったのに、女目当ての彼らは途中別行動とってナンパに勤しみに行ったらしい。きっと無駄な努力に終わるだろうけれど。勢津子さんと二人で回らせると違う意味で怖いなぁと思う将志だった。どこかで大学生に声かけられたりしてないだろうかと心配になる。本当は学祭に呼んで、先輩やほかのやつらに会わせたくなかったのが本音。
(槇乃さん絶対に大学生受けするんだよ、あの大人っぽさとか、お姉さんぽいとことか...)
「許せん、お前今日は調理当番終日な!」
「そんな!先輩〜〜」
「けどお前ほど料理のうまいのもいねえからな、あきらめろ。今さっきオマエが抜けてから味が落ちてお客さんから苦情がでるわ、列はさばけないわでえらいことなんだ!頼むよ!!」
どうやらそれを頼むためにここまで将志を捜してきていたらしい。先輩に拝み倒されてがっくり肩をおとす将志だった。
「すみません、焼きそば2人前ください。」
仕方なく焼きそばを焼き続ける将志の前に立った、落ち着いた雰囲気の女性、槇乃さんが上手に歳を重ねたらこんな感じになりそうだなと将志はちらちらと盗み見ていた。
「奈津美、飲み物コーヒーでよかった?」
どう見たってこの間まで大学生ってくらい若くてかっこいいお兄さんがそういって近づいてくる。少しだけ足を引きずっている。
「み、三谷先輩!!!」
「ああ、磯部か?久しぶりだな。元気だったか?」
「お久しぶりっす!あの園村とは?」
「さっきまで一緒だったよ。OB戦でたんだが、運動不足が祟って前半で足つらせてしまったんだ。」
将志は隣にいたキャプテンが少年のように目を輝かせて話すその青年を見た。背も高く、がっしりとしていてそれでいてしなやかな体つき。さわやかな好青年、だけれどもその笑顔は甘く女性を引きつけてならないだろう。
「ああ、広野、この方はな、この大学の卒業生で、ラグビー部のキャプテンだったんだ。すっげえ、格好よくってな、女性にもモテモテで...あっ」
磯部はしまったと言った顔をした。
「いいのよ、聞いてるから...」
にっこりと笑うとやわらかい女だった。左の指に指輪?不倫?それともまさか...
「あの、お二人は結婚なさってるんですか??」
「え、ええ...?」
将志の勢いに押されて二人は頷いた。
「ほんとですか?あれだけ入れ食い状態だった三谷先輩が一人に絞るなんて...すげ、はや...」
磯村は感心しどうしだった。真剣な目をして三谷を見つめる将志に気がついた彼は将志を三谷に紹介したのだ。
「あ、こいつ今年入った1年で、結構有力株なんですよ。可愛い顔してるのにけっこうえぐいサッカーしてね、先輩であろうがお構いなしにチャージかけてくる元気もんです。」
そう紹介されて三谷に思いっきりさわやかに微笑まれた。
「すんません、ちょっとだけ!!」
将志は飛び出すと、三谷の腕を取って焼きそばの列をほったらかしてその場を離れた。
「あの、聞きたいことがあるんですけど、いいですか?!」
そのただならぬ雰囲気というか勢いに押されて浩輔も思わず頷いてしまう。
「あの、カノジョさんていうか、奥さん年上ですよね?あの、どうやってプロポーズしたんですか?どうやってOKしてもらったんですか?」
「は?あの...君、もしかしてカノジョ年上?」
「そうなんです!だから、どうしても聞きたくて!オレ、まだ大学入ったばっかりで、カノジョは幼馴染なんだけどもう社会人で、待たせなきゃならないだろうし、でも、待ってもらえるかどうか不安で...」
素直な視線の将志の気持ちを受けて浩輔はにこっと微笑むと耳打ちした。
「そう...けどね、女性のほうがもっともっと不安なはずだから、いっぱい愛してあげるのがいいよ。それとココをしっかり磨いて、包み込めるおとなになれよ。」
そう言って浩輔は左の親指を立てて胸のあたりをくいっと指し示した。心を鍛えろと言うことか…
「背伸びするんじゃなく、しっかりと足を地につけてね。ま、僕もえらそうに言えないけどね...幾つ年上なの?」
「えっと、5歳です...」
「じゃあ、まだ23.4ってとこかな?結婚焦るほどじゃないよ。うちのオクサン若く見えるけど、あれでも33だから...内緒だよ、10上なんだ。」
「ええっ??」
将志は思わずそっちを見るけどとてもそうは見えない。
「ま、僕が惚れて口説きに口説いてやっとだからね...なかなか結婚してもらえないかと思ったけど、それは彼女の遠慮だったんだよ。女性は男性より年上なこと、僕らが思ってる以上に気にしてるからね、出来るだけ安心させてあげないとね。やっと結婚してもらえたんだけど、それでも今は悲しいかな単身赴任中でね、離れてると不安にもなったけど、ようやく最近離れてても安心していられるようになってきたとこかな?」
「そ、そんなもんですか?」
「ああ、だから、惚れてるなら離すなよ、1年坊主。」
そういって将志は三谷にぱんと肩をたたかれた。
「槇乃さん、ごめん、もうすぐ終わる。」
メールで最終近くまで焼きそばを焼くことは連絡してたので、終わりがけになると槇乃だけがその場に現れた。裏に回ってもらって少しだけ話が出来た。もう怒ってないらしい。
「いいよ、待ってる。」
「博士たちは?」
「ナンパに失敗して寂しく帰ったよ。」
「そっか、じゃあ、槇乃さんだけ待っててくれたの?」
「...うん。」
ちょっと照れた風な槇乃に将志は思わず嬉しくなる。居づらいだろうに、ずっと待っててくれるんだと思うといても立ってもいられない。
「おい、もういいぞ、帰っても...将志、今日はがんばったな、ゆっくり休めよ。カノジョさんもすんませんでした。こいつ引き取ってやってください。」
「先輩...後かたづけは?いいんですか?」
「そんなもん、ろくに働いてない2年の馬鹿どもにやらせるよ。さっさと帰れ!こんなとこで見せつけられたら独りもんに目の毒だからな。」
そういってさっさと追い出された。
「槇乃さん、またしてごめん、それと、今朝も、さ...」
「そんなに謝らなくていいわよ。その、焼きそばおいしかったし...」
「オレさ、本当は...槇乃さんを学祭に呼ぶの怖かったんだ。一番ぺーぺーで先輩にこき使われてるし、学生のオレを見せるの今更ってかんじで...早く社会人になりたいけど、そんなの一足飛びに越せないし、だから今朝もこのまま来れないように槇乃さんに無茶して...ごめん。」
「いいよ、そんなの...それよりもあたしみたいな年上の女が学祭に顔出したら迷惑かなって思って、連れ探して勢津子呼び出したら、博士らまで来ちゃって...」
「迷惑じゃないよ!オレ槇乃さん、見せびらかしたいもん!だけど、オレみたいな頼りないのじゃ槇乃さん恥ずかしいかなって...」
「まーくん...」
将志の胸によみがえる三谷の言葉。『女性のほうがもっともっと不安なはずだから、いっぱい愛してあげるのがいいよ。』そうだいっぱい愛せばいいんだ。自分のもてる力一杯で。
「あのさ、早くうちに帰ろう?いい?」
そのいいの意味するモノは...あの大先輩の言葉を単純にとった将志だった。
いや、そういう意味だけじゃないことも判ってはいる。けれども今の自分に精一杯出来ること。それは...
「いっぱい愛してあげるからね?」
にっこり笑う将志にかなわない槇乃だった。
「もう、やぁ...許して...」
「だめだめ、旅行前だからって、何日もオレの部屋に来なかったのはだれだ?」
夕食の後、早々に予約したホテルに戻った紗弓と遼哉だった。
「だって、バイトもしなきゃだし、あんまり頻繁すぎると...親はいいんだけど、お兄ちゃんが五月蠅いんだもん。」
「はん、自分だってしっかり教え子に入れ込んでるくせに、あのエロ教師がっ!」
「真名海ちゃんはいい子だよ?お兄ちゃんも外泊したりさせたりしてないみたいだし...あんっ」
「けどしっかり手出してるだろ?アレでよく学校でばれねえよな?」
「わ、わかるの??」
会話しながらだけれども遼哉の愛撫がやむことはない。
「当たり前だろ?雰囲気でバレバレ。和兄あの子にめろめろだろ?」
「それは...」
「オレは紗弓にめろめろなの!1.2回で離してもらおうなんて甘いな。」
「ひゃぁん、でもこんなのいやぁ...逃げないから、ゆるして...」
両手首を大きめのハンカチで括られて両手の自由のきかないまま、脚の間に顔を埋めた遼哉にしつこく攻められてる紗弓だった。何度か達しそうになる前に引き戻されもう意識もぐらぐらになる寸前だ。
「大丈夫、朝までには何とかしてやるから、な?」
「そんなぁ...」
涙目で訴える紗弓だった。もっとも遼哉だってそんな紗弓に朝まで持つとは思ってはいない。メロメロなのはこっちだと思った。ただあの映画屋のぽそりと言った言葉が気になったのだ。
『あんたは演技してもしなくてもその本質がフィルムに映ってしまうな。それに比べるとあの子、あんたのカノジョは素直だね。そのまま映って見えるよ。微笑んで柔らかい...だけどちょっと縛って泣かせるかしたら見てる男が全員あの子を守りたくなるだろうな。』
そう言われて一瞬紗弓を攻めているときの泣きそうなほど感じてるカノジョのすべてを思い出して焦った。久我はファインダー越しに何もかも見透かすのだろうか?
『それはオレだけで十分さ。あんただって、あのかっこいいカノジョを女にする瞬間をほかの誰にも味あわせたくないだろ?』
『...当たり前だ。』
二人はにやりと笑ったが目は全然笑っていなかった。
そのころ...
「やっぱ隣の部屋はやめた方がよかったんじゃ?」
「だって一緒に予約とったら隣になってたんだもん。」
竜次と芳恵もしっかりその後の格好をしてるのだが、いかんせん隣が激しすぎる。
「相変わらず遼哉のいじめ方ってすごいよね...」
時々聞こえてくる悲鳴に近い紗弓の高まったかわいらしい声。きっと遠慮なく遼哉に攻め立てられてることは見えなくとも判ってしまう。
「あ、ああ...あのさ、芳恵もああいう風にされたい?」
まじめな顔で竜次が聞く。
「まさか!あたしは...その、普通に、竜次くんでいい...」
「ほんと?」
「うん、ね、ほんとに今夜泊まれるの?」
「ああ、ちゃんと外泊届け出してきた。朝まで一緒にいられるよ、芳恵...」
そっと重なる唇。いつもの遠慮しがちな、今村らしいキスの仕方。
「だけど、オレも遼哉と変わらないかもしれないな...」
「なんで?」
「ごめん、芳恵、オレももう一回...次いつあえるか判らないんだから、オレとしてはこのままは眠れない。」
照れて真っ赤になりながらもそう告げる不器用でまじめな恋人をじっと見つめる芳恵。
「だ、だめか?」
不安になって思わず聞き返す今村に頭を振って違うと返事する。
「あの二人ほどっていうのはやり過ぎな気もするけど、あたしらはあたしたちなりに、そのあ、愛し合えたら、いいなぁって思うの...だから、竜次のしたいだけ、いいよ。」
「芳恵っ!」
がばっと抱きつかれて芳恵は苦しそうにもがきながらも内心嬉しかった。
翌朝まともに起きれなかったカップルはさて何組でしょうか?
Fin
| この話は記念作なので、諸処の設定の違いなどつっこみはなしでお願い致します。(笑) |